
コメの高騰を受け、価格高騰回避のために29道県が増産へ
コメの高騰を受け、29道県が24年産の実績より増加を見込んでいるとのこと。
2025年の主食用米の生産量について各都道府県が目安を公表し、29道県が24年産の実績より増加を見込んでいることが22日、分かった。昨夏の品薄や民間在庫の低迷が後押しとなり、増産へとかじを切る産地が相次いだ。25年産の流通量が増えれば、さらなる価格高騰は回避される可能性もある。人口減で長期的なコメの需要は減少傾向にある中、多くの産地が異例の判断をした形だ。
減少は9県にとどまった。
農林水産省が各地の具体的な数値を「マンスリーレポート」にまとめた。その数値と、農水省が昨年12月に公表した24年産の収穫量実績を単純比較して増減を調べた。都道府県ごとに生産量目安の算出方法は異なり、ほぼ全てが政府備蓄米の放出表明前に決まった。
目安の公表時期は異なるが、23年産で増加を見込んだ産地は20県、24年産は26県だった。
25年産で増加を見込む産地のうち、生産量の多い新潟県が3.5%増の56万2400トン、山形県が6.8%増の32万6300トンだった。北海道は微増。九州地方では大幅に増やす県が目立った。
非常に重要なことだと思う。しかし、長らく放置していた休耕田の復活はそう簡単ではないと聞く。国も積極的に関わり、自治体と共に支援するようにして欲しい。
それと、コメのサイドビジネスが要因の一つと言われているが、国は原因究明をしっかり行い、対応していただきたい。
ネットの反応
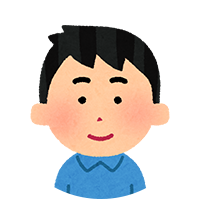
コメの在庫が減少している中で多くの道県がコメ生産を増加させることは決定的に重要である。農水省と官邸はその動きこそ支える必要がある。
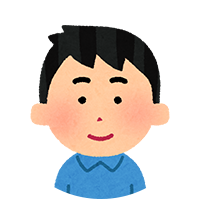
現在、耕作はしてないが休耕田 遊休田として生産組合が管理している農地を再耕してお米の増産活用は良いことであると思います。
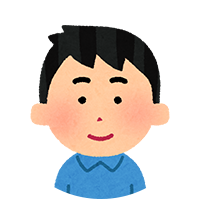
日本人にとって米が主食である米がサイトビジネスに利用され米の高騰で、家庭を圧迫している現実、高くて買えない国民の声は届いている。
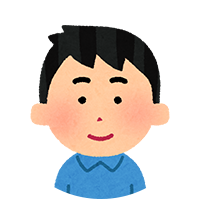
農家です。増産してもいいよと言っても、今まで他の作物なり荒らしていた水田に再度稲を作るのは口で言うほど簡単ではないと思う。以前に私は長く転作していた圃場を復田したことがあったが、その水田は土壌の肥料バランスが崩れてその水田だけまともな米が取れなかった。まあ一年や二年だけ転作してましたなんていう水田は良いだろうけど、上手く行けばいいですけどね。


