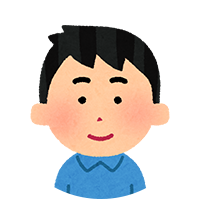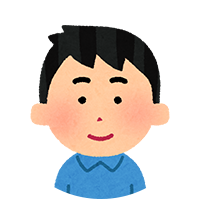政府、マイナ保険証利用の患者、電子カルテ情報を病院間で共有へ
「マイナ保険証利用の患者」がXでトレンド入り。
政府は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を利用する患者の電子カルテ情報について、医療機関同士で共有する新システムの運用を、2025年度に始める方針を固めたとのこと。
新システムは「電子カルテ情報共有サービス」で、厚生労働省所管の法人が管理する。各医療機関から、電子カルテに記録された病名やアレルギー、感染症と生活習慣病の検査や健診結果、処方薬の情報が集まり、データベースに蓄積される。データの保存期間は3か月~5年間となる。全国の医療機関がデータを閲覧するためには、患者の同意を得る必要がある。
新システムの導入で、救急患者の症状と、データをつきあわせて診断したり、初診患者の検査結果を、過去の数値と比べて病状の変化をみたりすることが可能になる。アレルギー情報は、安全な薬の処方に役立つ。
医療機関がシステムを通じて、別の医療機関に紹介状を送る機能も備える。患者が紹介状を入手する手間が不要となる。
全文はソースで
あくまでも、情報漏洩などのセキュリティ対策が万全であれば、メリットは大きいと思う。医療の質と安全性を高めるとともに、医療機関などが患者情報を共有するための紹介状が不要になるので、紹介状の費用が発生しなくなる。
一方では、すべての病院がシステムを導入する必要があり、中小規模の病院はシステムを導入するのが困難ではないかとの声もあがっている。
ネットの反応
電子カルテの共有は医療の質と安全性を高め、医療を受ける側にも提供する側にも大きなメリットがあります。
マイナ保険証利用の患者、電子カルテを病院間で共有へ…病歴や検査結果も把握可能に(読売新聞オンライン) https://t.co/2KJ8BdL3P3
— 福田とおる 国民民主党 衆議院議員(愛知16区) (@Toru_Fukuta) November 28, 2024
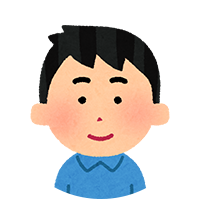
紙の紹介状という100年前の仕組みが動いてるんがおかしいから
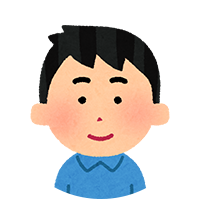
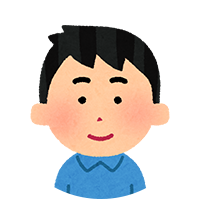
こうした個人情報の流出などのセキュリティ対策は、果たして万全なのかという国民の懸念はいまだ払拭されてはいない中で、こうした利便性ばかりが取りざたされるという事には抵抗のある方もいらっしゃるものと考えられる。