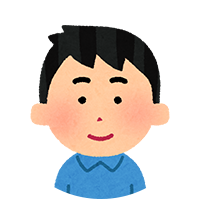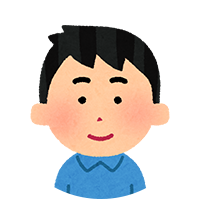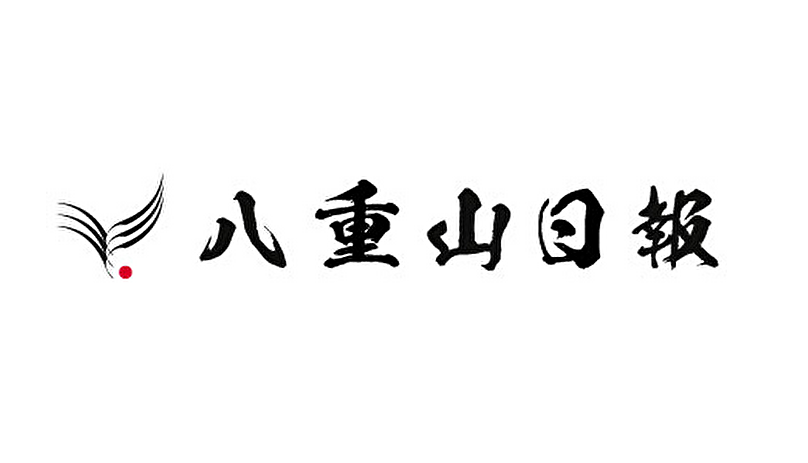
八重山日報「「オール沖縄」は存在意義を失った」
「「オール沖縄」は存在意義を失った」と八重山日報。
改めて「オール沖縄」は終焉(しゅうえん)に近づいているとの思いを強くする。26日投開票の沖縄市長選で、自民、公明が推薦した前県議の新人、花城大輔氏が、社民、共産、立民、社大推薦の「オール沖縄」の対立候補を破り、初当選した。今月の宮古島市長選でも、保守系新人で県知事公室長などを歴任した嘉数登氏が「オール沖縄」に支援された現職の再選を阻んだ。「オール沖縄」は今年に入り、2連敗となった。
沖縄市、宮古島市の市長選で、玉城デニー知事を支える革新勢力は既に「オール沖縄」という呼称を前面に出していない。
昨年の衆院選でも革新勢力は、選挙演説などで「オール沖縄」「辺野古」というワードを封印する傾向が見られた。
「オール沖縄」が沖縄の選挙を席巻した時代はもう終わった。選挙戦で「オール沖縄」を掲げるメリットがほぼなくなっているからだ。革新勢力を「オール沖縄」と呼ぶこと自体、場違いになりつつあるのかも知れない。
「オール沖縄」はもともと、保革を問わず米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する政治勢力の呼び名だった。
産みの親である翁長雄志前知事が健在の時代は保革共同体としての機能を一定程度、果たしていたが、革新色が強まる中で保守側の人材が次々と離脱。革新勢力に先祖返りした。
保革を問わず県民の支持を広げてきたはずの「オール沖縄」が衰退した理由は何か。辺野古移設工事の進展、辺野古を巡る裁判闘争での敗北で、辺野古移設阻止が現実的な政策とみなされなくなりつつあることが第一に挙げられる。
加えて物価高などで県民を取り巻く経済環境が厳しさを増し、選挙戦でも基地問題より経済問題が重視されるようになった。
玉城県政も辺野古を巡る最高裁判決の無視、県ワシントン事務所に関する不祥事、さらには北部豪雨災害の初動の不手際など失点続きだ。以下ソースで
「オール沖縄」系市長ゼロ、県議会野党過半数、では「オール沖縄」という看板に偽りありだ。
記事でも指摘されているように、玉城知事の行動がマイナス要因に働いている。米軍や基地問題には以上に速い反応を見せつ玉城知事だが、公約の達成率は今どのような状況だろうか?2022年6月27日の沖縄県議会一般質問で、「291のうち完了8、推進中279」と説明し、島袋大県議から公約の達成率は「2.7%」ではないかと指摘されていたが、現在はどうなのだろうか。
沖縄県政の停滞も「オール沖縄」の衰退の大きな原因だろう。
ネットの反応
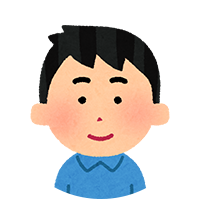
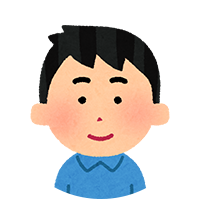
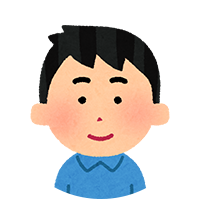
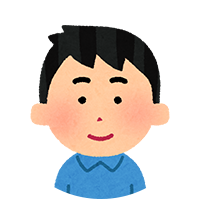
昨今はやってますね。基地問題もそうでしたね。
正直、そのような情緒主義はほかの国でやっていればよい。