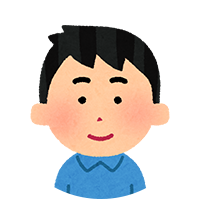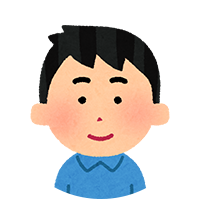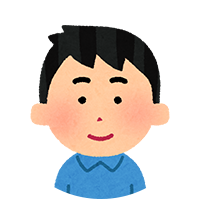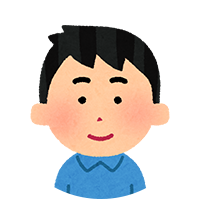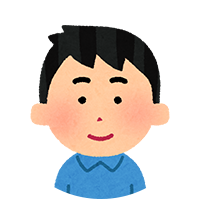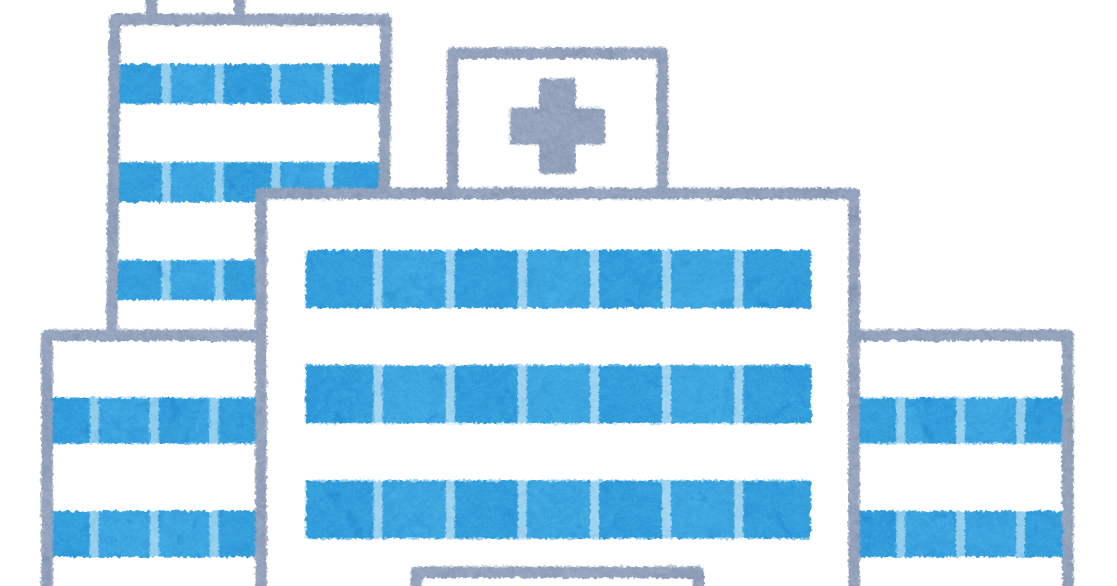
各地の国立大学病院が経営危機に直面。令和6年度の赤字総額は200億円超で、病院関係者ら「このままでは地域医療が崩壊する」
各地の国立大学病院がピンチだという。
各地の国立大学病院が経営危機に直面している。令和6年度の赤字総額は200億円を超え、病院関係者らには「このままでは地域医療が崩壊する」との危機感が広がる。高度医療を提供し、医師育成や地域病院への医師派遣も担う医療界の「心臓部」で、一体何が起きているのか。
■物価上昇など影響
「より一層悪化している」。今年5月上旬、東京都内で開かれた国立大学病院長会議の記者会見で、大鳥精司会長(千葉大医学部付属病院長)は窮状を訴えた。
国内42の国立大学病院の6年度収支決算(速報値)は、全体の6割にあたる25病院で現金収支がマイナスに。42病院の赤字総額は前年度(26億円)を大きく上回る213億円に上った。
背景には、経営環境を巡る厳しさがある。エネルギー価格や物価の高騰により、光熱費や材料費、医薬品費などが軒並み上昇。働き方改革に伴う残業時間の正確な把握や職員の処遇改善を一部行ったこともあり、人件費の負担増にも直面した。
「限界にきている」「潰れる病院が出かねない」。会見に臨んだ各地の病院長からも、悲痛な声が次々と上がった。
■経営努力で増益も…
東京医科歯科大病院から名称変更した東京科学大病院(東京都文京区)は、5年度に約11億円の赤字を計上。6年度の赤字額は30億円以上に膨らむ見込みだ。
収支改善に向け、手をこまねいていたわけではない。職員宿舎の一部解約を決めるなど、コスト削減を推進。対応は、職員らが着用する白衣を病院支給から自腹購入に変えるといったものにまで及ぶ。
各診療科の初診枠を拡大させたり、手術数を増やして入院の受け入れを強化したりと増益に向けた取り組みも強化。新型コロナウイルス禍(2~4年度)に6~7割台だった病床稼働率は現在、8割台まで回復し、コロナ禍前の元年度と比べて6年度の医業収入は約55億円増となった。
ただ、こうした努力にもかかわらず、光熱費や人件費などの固定支出は約73億円も増えた。情報システム更新などにかかる費用も重くのしかかる。採算面を考慮し、来年度は一部病棟の閉鎖にも踏み切るという。
国立大学病院は地域医療に貢献しているので、国が支援してても残すべきと思う。それと、国立大学病院は、国立大学の医学部が運営する病院。国立医学部は学費が安く、私立医学部は学費が高い傾向にある。国立大学病院が経営難で減少してしまうと、国立医学部にも影響が出てしまうのではないだろうか。もしそうなってしまうと、お金持ちしか医師を目指せなくなるかもしれない。
ネットの反応